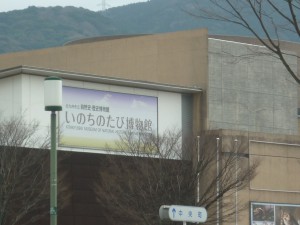新着情報リスト
いのちのたび博物館/知的障害者当事者と意見交換
2016年2月24日
「いのちのたび博物館」/ユニバーサル化で知的障害当事者と意見交換
北九州市の「いのちのたび博物館」では2月14日、知的障害のある青年たち3人から博物館の展示の在り方や職員の対応などについて意見を聞いた。同館は高齢者、障害者、外国人等にも親しまれる博物館を目指し、2年がかりでユニバーサル化事業を進めており、今回の取組みもその一環。育成会から大石翔平さん、大庭竜彦さん、辰島和義さんが参加した。
同館は正式には北九州市立自然史・歴史博物館といい、地球誕生(35億年前)以来の生命の進化と人の歴史を展示解説している。年間の来館者は45万人を超えるといわれ、児童生徒をはじめとする一般市民のほか最近は他県や海外からの来館者も増えているという。特に人気があるのが自然史系・中生代の恐竜の展示で、白亜紀の北九州を再現した360度体感型ジオラマを擁するエンバイラマ館はそのスポットのひとつ。また、新生代コーナーに展示されている5000万年前のブロントテリウムは日本で唯一の実物化石とされ、人気を集めている。
一方、歴史系では北九州市の三大夏祭りのほか、明治時代の農家と農具、古代住居と昭和30年代の住居等が展示されているほか、「路」がテーマの展示館では銅矛、装飾古墳、黒田24万騎画像、山本作兵衛炭鉱記録などを展示して、同市の歴史の歩みを学ぼうとしている。
この日、同館の学芸員の案内で館内を観覧した3人は、それぞれのコーナーの前で展示物や展示の仕方、さらには災害など緊急事態への対応等について感想を述べるとともに、見学後は学芸員と懇談した。この中で、3人からは「現代における電子機器や文房具の変遷が理解できるコーナーがほしい」、「地震など災害時の対応は大丈夫か」、「エンバイラマ館では音声や暗さで入館者がパニックを起こさないか」といった感想や意見が述べられた。
カテゴリー:その他
就労対策委員会学習会
2016年2月23日
就労対策委員会/共生社会と差別解消法で学習会
育成会の就労対策委員会(吉武千恵子委員長)は2月18日、「共生社会」と障害者差別解消法について学習した。育成会活動にとって最重要なテーマとなるもので、講師は北原守会長が務めた。
「共生社会」の実現は障害者制度改革の目的であり、一方で差別解消法は「共生社会」実現に必須の法制度で、しかもこの4月から施行されることなどから、両者への理解促進は避けて通れない課題となっている。
この日は、「共生社会」についてはその実現に向けての活動を中心に、また差別解消法では、法の仕組みと新たな差別を生みやすい「合理的配慮」について学習した。
このうち「共生社会」実現への取組みでは、この際の「社会」はわれわれが今いる「場」を言い、具体的には家庭、学校、職場、地域等を指すことを確認するとともに、社会の縮図でもある地域を共生の場にするには、地域住民との交流、地域行事への参加、地域への貢献活動を通して信頼関係をつくっていくことが最も大切なことを学習した。その上で、共生の地域づくりには全ての人たちが主体性を持ち、自分のできる時に、自分にできるところから始めることが肝要なことも学んだ。
一方、差別解消法では、①差別には障害を理由とした不当な取り扱いと、②合理的配慮に欠けた対応とがあり、国や地方自治体の行政機関では①②が禁止の対象となるものの、民間事業者は禁止は①のみで、②の合理的配慮は努力規定となっていることを学んだ。その上で、合理的配慮は環境を見直すことで障害者も健常者と同じように地域・社会生活が可能になるという「社会モデル」からくるもので、障害者側が環境の見直しを求めたのに対し、行政・民間事業者側が過度な負担を感じない範囲なのに適切な配慮を提供しなかった場合に差別として扱われることも学習した。
また、差別解消法では相談や紛争の窓口として、行政機関、医療・福祉事業者、研究者、障害当事者等で構成する「地域協議会」の設置をうたっており、この日の学習会では、北九州市の取組みについても報告があった。
カテゴリー:その他
若松工芸舎支部/「家族支援」で学習会
2016年2月22日
若松工芸舎支部/「家族支援」で学習会
育成会の若松工芸舎支部(青木悦子支部長)で2月18日、知的障害児者を持つ家族(親・兄弟等)の支援について学習した。昨年11月に育成会がまとめた提言を踏まえて行ったもので、講師は北原守会長が担当した。
育成会では、一昨年12月に「家族支援を考える会」を設置、約一年かけてその在り方を協議し、昨年11月に提言をまとめた。その上で、シンポジウムを開いて内容を公表するとともに、北九州市に対して、①相談支援体制の充実、②特別支援教育の充実、③親亡き後も含めた本人自立支援サービスの充実の重点3項目の実施を申し入れた。
今回の提言の特徴は、「家族支援」の方向を障害当事者(本人たち)へのサービスの向上にとどめず、家族の資質や介護スキルの向上、さらには共生のまちづくり等によって家族の負担軽減を打ち出しているところにあるが、対象とする範囲が広いことなどから今後も検討を重ね、具体策の充実を図ることにしている。特に、後半の家族の資質や介護スキルの向上、共生のまちづくり等による負担の軽減は先進事例も乏しく、北九州育成会独自の打ち出しになるものと思われる。
この日の学習会では、「家族支援」の二つの方向を確認した後、家族の資質・スキルの向上や共生のまちづくりがどのように家族の負担軽減につながっていくかを学習した。この中で、例えば本人たちの意思決定支援では、家族が本人たちを受け入れる寛容さとコミュニケーション力を高めることで支援はより充実し、結果として家族の負担は軽減する。また、共生の地域づくりを進めることで家族・本人への支援も広がり、引いてはそれが家族の負担軽減にもつながるとして、地域との交流・貢献活動の大切さを学習した。
カテゴリー:活動報告
地域生活対策委員会活動報告
2016年2月19日
地域生活対策委員会活動報告/いのちのたび博物館見学
北九州市いのちのたび博物館がユニバーサル化を目指しさまざまな取り組みをされていて、北九州市手をつなぐ育成会(親の会)へも聞き取り調査や講演の依頼が行われたことは、前述のとおりです。子ども達が当たり前に地域で日常生活を送ることができるようにと親の学びを重ねている地域生活対策委員会でもこのユニバーサル化に関心を持ち自分たちでも考えてみようということで2月12日(金)に見学に行ってきました。
いのちのたび博物館は、北九州市八幡東区東田2-4-1にあり、さまざまな生物を太古から現在まで学べる自然史ゾーンと主に北九州市の歴史や暮らしを学ぶ歴史ゾーンがあり、壮大な展示物と資料から、いのちのつながりを学ぶことができる貴重な学習の場となっています。当日は、委員会のメンバー4名が参加しましたが、大人だけで行くということは、初めてでゆっくりと見学できたことに、感激したほどです。障害のある子どもを連れての外出は、ある程度の緊張感を持ちつつ、子どもが混乱しないだろうか、機嫌を悪くしないだろうかなど考えて自分の気持ちは置き去りのままであることに気づかされました。
施設内では、展示物の効果のため薄暗い場所も多く自分の子どもには難しいかなと感じたり、順路や誘導がわかりにくかったり、展示説明の文字が小さくて障害者だけでなく、高齢の方もわかりにくいのではなどの意見がでました。
その後は、見学を終え、場所を移し昼食を兼ねてのディスカッションを行いました。博物館だけでなく他の外出先でも困るのが母と息子、父と娘など異性同士で出かけた場合のトイレ事情。特に介助者側がトイレに行きたくなった時など本当に切実な課題です。子どもが小さい時は一緒に入った経験もありますが・・・。特に一人で待つということができない場合、見失ってしまうこともあります。今、そばに居たはずなのに一瞬、目を離したら居なかったという怖い経験をされたかたも多いはずです。近い将来、博物館など公共の施設では、コンシェルジュ的な何でも気軽にお願いできる方がいてくれたらと願います。
しかし、障害児者の親として一番きつく辛いと思うことは、人の視線です。大きな声を出したりジャンプしてしまうなどの障害特性に向けられる鋭い視線とお叱りは、気持ちを強く持っているはずの親でさえも結構辛く、外出を後悔させてしまうほどです。
そういえば見学中、見かけた特別支援学級の子ども達の中にも声を出したり列から離れてしまう子もいましたが、私たちには、その姿が微笑ましく、むしろ博物館の雰囲気を楽しんでいる子ども達を嬉しく思いました。そして気づきました。私達のように障害を理解して見守っていてくれる人が街中にたくさんいてくれたなら私達の子どもは、どんな場所でも自由に楽しむことができるはずだということ。そのためには、やはり多くの理解を求め、啓発していくことが大切なんだと親の会の重要性を再確認しました。
カテゴリー:活動報告
いのちのたび博物館~親の会と意見交換
いのちのたび博物館ユニバーサル化事業~親の会と意見交換~
1月28日、ユニバーサル化に向けた意見交換会へ育成会から久森栄子、國家綾子両副会長と岩橋由美子さん(門司地区)の3名が出席し、担当職員の説明を受けながら展示コーナーやトイレなどへの案内がわかりやすくなっているか、使いやすい装置になっているか等を確認しました。また休憩場所が知的障害者にとってクールダウンする部屋として利用できるよう配慮してほしい事、障害者向けのワークショップや障害者施設のクッキーやケーキなどの販売ができるよう「共生の場」作りへの協力をお願いしました。
当日は4名の職員が、私達の話に熱心に耳を傾けて「博物館が決して特別なものではない、楽しい場所としてインプットできるよう工夫を凝らしたい」と熱く語る姿勢に「ユニバーサルミュージアム化事業」への期待が膨らみました。
カテゴリー:その他